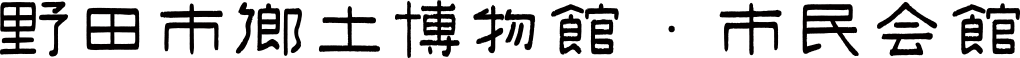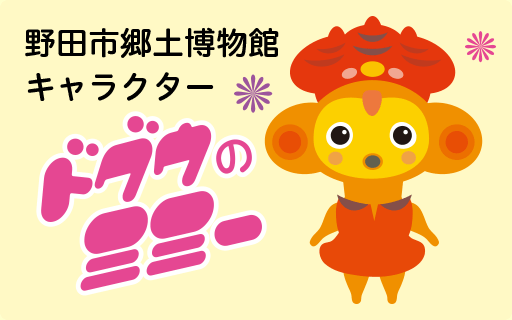令和5年4月29日のリニューアル以前の常設展のコーナーと主な展示資料をご覧いただけます。
「野田に生きた人々の生活と文化」をテーマに、野田において醤油醸造業が本格的になる近世中期(18世紀)から1950年代までの時代を、当館コレクションを用いてコーナーごとに紹介していました。
期間:平成23年1月4日~令和4年9月19日(以後、屋根改修工事及び展示替えのため休館)
はじめに
現在の野田市は、周囲を利根川、江戸川、利根運河という三つの河川によって囲まれた、全国的にも珍しい土地です。この地で、人々はどのように暮らしてきたのでしょう。
この常設展示では、醤油醸造が本格的にはじまる江戸時代中期から、伝統的な暮らしが大きく変化していく昭和30年代までの約350年間について、野田に生きた人々の生活と文化をご紹介します。
【二つの川と河岸】

17世紀の中頃、野田の町が誕生、発展していった背景には、利根川、江戸川という二大河川がありました。
牛馬や人力しか陸上輸送の手段がなかった当時、川船による水上輸送は安く大量の荷物を運ぶための有効な手段でした。このため今上(いまがみ)、中野台(なかのだい)などの船の発着場(河岸・かし)には東北と北関東の年貢米、各地から届いた小麦、大豆、塩などの醬油原料、そして江戸へ出荷される醬油など大量の物資が行き交いました。また荷物の積み下ろしを管理する問屋、船を操る船頭、荷物を運ぶ人々などでにぎわったのです。
主な展示資料
- 高瀬船(模型)
- 江戸川の高瀬船
- 郷村高反別并銘細書上帳
- 川岸問屋御運上御請并仲間定書帳
【醤油の町 野田の名声】

野田の醬油造りは、寛文元年(1661)の上花輪(かみはなわ)村・髙梨兵左衛門(たかなし ひょうざえもん)家が記録の残るもっとも早いものとされています。
18世紀に入ると、地元の豪農や資産家を中心に醬油造りが盛んになり、天明元年(1781)には醸造家7軒が造醬油仲間を結成、醸造業の発展に尽力しました。18世紀まで江戸の町では関西産の醬油が主流でしたが、19世紀には関東産の濃口醬油が優勢になり、利根川、江戸川の舟運を背景に、野田は銚子と並ぶ一大産地へと成長を遂げました。
主な展示資料
- 関東醤油番付(天保11年版)
- 醤油醸造絵馬
- 和漢三才図会
- 御本丸西御丸御用立札
- 御膳御用箱
- 御本丸西御丸御用額
- 田安一橋清水御膳御用額
- 銭箱
- 千両箱
【醤油造りの道具】


主に明治前期(19世紀末)まで行われた手作業による醬油造りでは、多数の道具が必要でした。明治18年(1885)の千葉県の調査書には、87種類もの道具が記録されています。これらは、ほとんどが木材や竹などの自然素材でできており、運ぶ、かき混ぜる、注ぐといった機能にあわせて、蔵人(くらびと)たちが効率的に使えるよう工夫されています。
醬油蔵には、醬油造りを担う蔵人のほかにも、こうした道具を製作、修繕する桶工や樽工、蔵の修繕や器具の取り付けに関わる大工や鳶といった職人も毎日のように出入りしていました。
主な展示資料
- 醤油製造所絵図面
- 野田醤油作業模型
- 野田醤油作業模型(大豆を蒸す)
- 野田醤油作業模型(小麦を炒る)
- 野田醤油作業模型(仕込み)
- 野田醤油作業模型(攪拌)
- 野田醤油作業模型(圧搾)
- 野田醤油作業模型(火入れ)
- 麹蓋
- 叩き板
- ササラ
- 掻桶
- 担ぎ桶
- 担ぎ桶の使用風景
- 櫂竹
- 締木の先端
- 桃桶としぼり袋
- 柄長
- 漏斗と樽
- 樽に醤油を詰める
【醤油の印】

野田の醬油醸造家は、明治20年(1887)に野田醬油醸造組合を結成し、原料や商品の価格統制、博覧会への共同出品などを行いました。さらに組合内で醸造家同士の競争意識も刺激されることで、野田の醬油醸造業全体の躍進がもたらされました。
各醸造家は、それぞれ醬油の銘柄を示す印(商標)を用いて商売をしていました。なかでもその家の中心的な銘柄は「本印」と呼ばれます。その他にも等級によっていくつもの印を使い分けていました。大正の初めには、印の数は200種類以上にも及んだと言います。
主な展示資料
- 押絵扁額「野田醤油醸造之図」
- 大日本物産図会「下総国醤油製造之図」
- 野田組製造醤油出品広告
- 看板「天上」
- 商標目録
- 醤油印鏡一覧
- 醤油のラベル
- 醤油のラベル
- 醤油のラベル
- 阿弥陀如来像
【企業城下町・野田の発展】

大正6年(1917)、野田と流山の醬油醸造家8家が合同し、野田醬油株式会社(現在のキッコーマン株式会社)が誕生します。この時期から昭和初期にかけて、大きな工場を取り囲むように商店や住宅が並ぶ、企業城下町・野田の基礎がつくられたのです。
同社の設立を契機に醬油造りの近代化、機械化が一層進み、鉄道や道路などの交通網も整備されました。また学校、銀行、水道、講堂など近代的で大規模な施設が県内でもいち早く建てられました。商店街には洋品店、飲食店、娯楽施設など新しい商売も生まれ、町は活気に満ちていました。
主な展示資料
- 大日本職業別明細図之内千葉県(野田町部分)
- 中野台河岸の蒸気船
- 下町を走る人車鉄道
- 醤油樽を載せたトラック
- 空から見た第17工場周辺
- 野田尋常高等小学校
- 給水所
- 興風会館
- 東葛飾郡案内記
- 千葉県東葛飾郡野田町勢一班 第拾壱回
- 中野台・戸邉回漕店文書
- 北総鉄道沿線案内
- 野田運送店営業報告書
- 財団法人興風会要覧
- 醤油王国 味合帳
- 野田尋常高等小学校増築校舎記念帳
- 山崎式醸造機械型録
- 野田醤油株式会社案内
- 祝 総武発展全線開通広告
- 商売繁盛双六
【醤油樽と職人】

昭和30年頃まで、野田では醬油の容器である樽の製造が盛んでした。
江戸時代から明治中期までは酒樽や一度使用したものの再利用が中心でしたが、大正期には新しい樽の使用が一般化します。昭和初期には工場や樽屋で年間200万樽以上生産されました。しかし同時期に缶やビンの使用がはじまり、昭和30年代に入ると小売に適したビンが主流になりました。これによりほとんどの樽屋が廃業しましたが、なかには漬物樽や民芸品などに活路を見い出した樽職人もいました。
主な展示資料
- 九升樽
- 竹削銑
- 側切鋸(上)と廻し引鋸(下)
- 正直台
- 馬と胸当て
- 締木と木槌
- 鉋
- 内鉋
- もと切銑
- 銑掛(複製)と道具
- 側板を削る
- 結い立て
- 製樽就業掲示板
- 白ビン「上十」
- 2リットルビン
- 8リットル缶
【近代の農業】

明治期から昭和30年頃まで、野田町以外の村々では、大半の人々が農業に従事していました。作業は主に人力と牛馬に頼っていたため、多数の人手が必要でした。
利根川と江戸川沿いの低湿地や谷津には田んぼ、台地上には山林と畑が広がっていました。作物は米が中心で、川沿いの土地は洪水などの被害に遭うことも多く、一毛作でした。一方、台地上の畑では二毛作も行われ、醬油の原料である小麦や大豆が多く作られました。他に煙草や養蚕用の桑、主に自家用と野田周辺で消費する芋類や白菜、大根などの野菜が作られました。
主な展示資料
- 足踏式脱穀機
- 唐箕
- 万石どおし(マンゴク)
- 踏鋤
- 備中ぐわ
- 風呂ぐわ
- ハッタンコロガシ
- 田植えの準備
【戦時下の生活】

昭和12年(1937)に日中戦争、さらに昭和16年に太平洋戦争がはじまると、生活は次第に制限されていきました。
野田には大規模な部隊や軍事施設はなく、空襲による大きな被害もありませんでした。しかし昭和15年を境に食物や衣類、燃料など生活に必要なものは切符制や配給制となり、入手が難しくなっていきます。一方で隣組、警防団、婦人会などの組織がつくられ、毎日のように兵士の見送り、防火訓練などが行われました。昭和20年に戦争が終わっても、物資に不自由する生活はしばらく続きました。
主な展示資料
- 軍服と鉄帽
- 慰問袋
- 自治組合回覧板控
- 防空チラシ
- 鉄鍋
- 真空管ラジオ
【暮らしの変化】

昭和25年(1950)、野田町と旭(あさひ)、梅郷(うめさと)、七福(ななふく)の各村が合併し、野田市が誕生しました。昭和32年には川間(かわま)、福田(ふくだ)の二ヶ村と合併し、さらに市域が拡大しました。この時期から経済的な余裕が生まれ、家庭で使う道具は、より便利で快適な暮らしを目指して大きく変化していきました。
市内では市営住宅や上下水道の整備が進み、昭和35年には都市ガスの一般家庭への供給が始まりました。白黒テレビが普及したのも同時期です。洗濯機、電話機などの家電製品も、昭和40年代にかけて一般家庭まで徐々に普及していきました。
主な展示資料
- 火鉢
- コテ
- 火のし
- 炭火アイロン
- 電気アイロン
- 交換式電話
- 有線放送電話機
- 洗濯板、たらい
- 手回し式洗濯機
【戦後の民主化と文化活動】

昭和20年代、野田には「野田読書会」「野田文学会」など多数の趣味や教養の団体が存在しました。昭和23年(1948)、これらの団体の提携、交流を目的として「野田地方文化団体協議会」(文協)が発足しました。
文協は、住民の文化活動が野田のまちをつくり、それが戦後の民主的な日本の再興につながるという熱意のもと、講演会、選挙啓蒙活動、展覧会開催などの活動を精力的に行っていきました。この野田市郷土博物館も、文協の博物館設立運動が契機となって、昭和34年(1959)に建設されたものです。
主な展示資料
- 野田美術展覧会目録
- 野田の史跡
- 食生活展覧会パンフレット
- 野田市郷土博物館資料展示会目録
- 興風会図書館 読書会チラシ
- 郷土博物館敷地図
- 郷土博物館室内図
- 郷土博物館建設特別委員会資料
- 当館設計案の変化(山田守の青図)
- 断面透視図
- 野田市郷土博物館模型 1/100
- 野田市郷土博物館落成記念陳列目録
- 薬師如来坐像